今回は、 溶解度パラメータ(SP値)一覧データベース_自動車ver についてまとめました。
趣味は車いじり
私は材料系のエンジニアとして、製造業(自動車産業外)で働く傍ら、趣味で車いじりをしております。
主に以下のことをやっています。
- カー用品店で購入した部品に取り替える
- 3Dプリンタで設計・製造したものに取り替える
メインはカー用品店で購入した部品を付け替えることをしていますが、自分のイメージしたものがない場合は、自ら部品を設計して、3Dプリンタで樹脂部品を作ったりもしています。
車いじり 課題
車の部品を純正品から変えてしまうと、本当に安全なのか?と感じます。
カー用品店で販売しているものは、製品の安全性を十分に担保して設計されていると思います(信じたいです)が、自ら3Dプリンタで作ったものは本当に大丈夫なのかと不安になります。
機械強度的には、製造した部品に応力集中するような微細な切り欠きがなければ問題ないと考えます。
また小生が材料の専門家なため、熱や湿度などの環境要因を顧慮した、材料選定及び部品設計をしているため、環境に起因した問題も起こる可能性は低いのかなと思っています。
しかし、化学的な観点は知見が少ないため、自動車に使われる薬品が、3Dプリンタで作った樹脂部品に万が一かかった時に、本当に問題ないかが不明という課題がありました。
溶剤が及ぼす影響
樹脂部品に薬品がかかると以下のような変化が生じます。
- 樹脂に薬品がかかる
- 樹脂中に薬品が侵入する(薬品が樹脂に溶け込む)
- 樹脂が膨張する(薬品が分子鎖内に入り込む)
イメージで表すと以下になります。

樹脂に薬品がかかることで、樹脂部品は膨張します。
その結果以下の問題を引き起こします。
- 部品が膨張する(寸法が大きくなる)
- 機械強度が低下する(剛性、強度、衝撃性)
- 変色する
この結果、部品が破断したり、他部品と干渉したり、外観性が悪くなります。
溶解度パラメータ(SP値)とは
しかし材料には、こういった薬品の悪影響を受けやすい材料と、受けにくい材料があります。
この考え方を理解するためには、SP値(溶解度パラメータ)という考えを理解する必要があります。
SP値(溶解度パラメータ)とは、対象となる材料がどれだけ溶媒を吸収しやすいかを表す指標です。
材料と薬品には固有のSP値と呼ばれる値があり、その値が近いもの同士は吸収しやすいということを意味しています。
詳細は以下の記事に書きました。
溶解度パラメータ一覧 自動車材料・薬品
つまり、自動車に使われる薬品のSP値を把握しておけば、そのSP値とは差異のある材料を選定することで、万が一薬品が材料にかかってしまった場合でも、材料の薬品吸収量は少なく、薬品の影響を受けにくいと言えます。
トヨタ自動車が親切に自動車で使われている薬品の詳細を公開してくれています。
このトヨタの情報をもとに、SP値をまとめた結果が以下です。

グラフに表すと以下になります。

これを見ると、以下が言えます。
- パワステオイルは樹脂材料とSP値が近い
- PA66樹脂はウォッシャー液、クーラント、ガソリンなどとSP値が近い
SP値が近いほど、材料は薬品を吸い込み(吸収)しやすいので、この表を見て注意する必要があります。
最後に
今回は、 溶解度パラメータ(SP値)一覧データベース_自動車ver についてまとめました。
主に樹脂やゴム材料、材料リサイクルに関してわかりやすくまとめておりますので、皆さんのご参考になれば幸いです。
ゴムや樹脂材料でお困りなことがありましたら気軽にコメントいただければ、分かる範囲でご回答させていただきます。
■化学系最大級の本サイトでの広告等の御依頼がございましたらご連絡ください
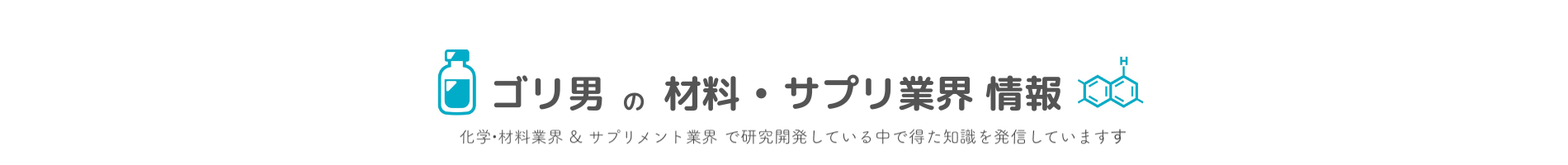

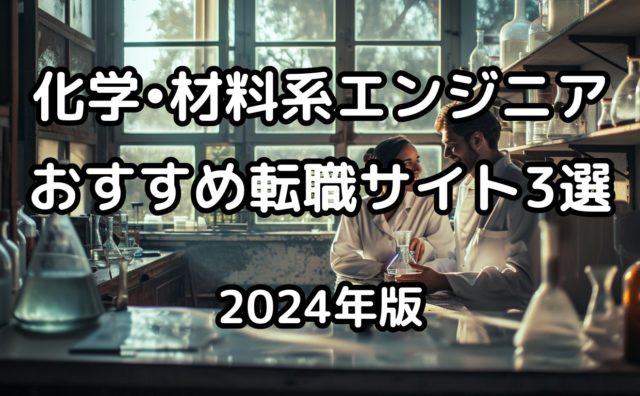


添加目的と補強効果.jpg)
