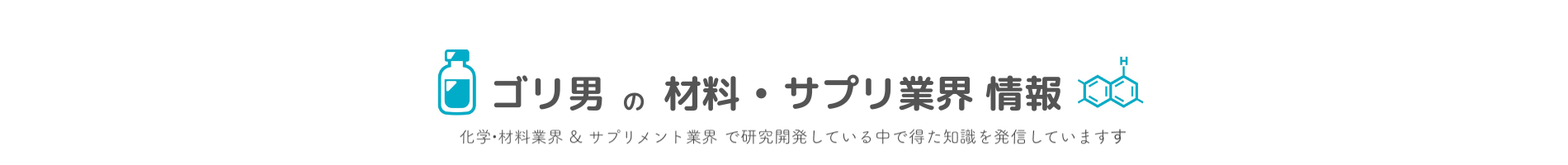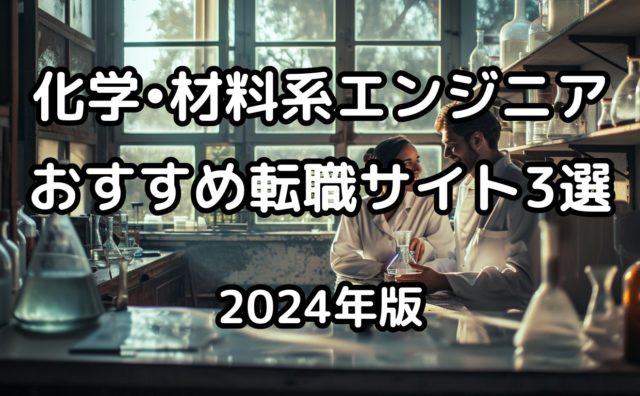今回は、【図解】樹脂の加飾方法まとめ について書きたいと思います。
加飾とは
プラスチック製品は、外観性を良くするため、一般的に塗装など製品表面に着色をします。
プラスチック自体の色は、材料の種類にもよりますが、乳白色や透明です。
商品性の観点から、プラスチックに何も加飾をしないで製品化をする例はほとんどありません。
通常はプラスチックを製品化をする上で、何かしら材料に加飾をします。
プラスチックの作り方については、別記事でわかりやすくまとめております。
樹脂 加飾方法
樹脂の加飾方法は、大きく分けて3つあります。
- 塗装
- 材料着色(材着・原着)
- マスターバッチ(MB)加飾
それぞれの加飾プロセスのフローチャートを以下に示しました。

(樹脂の加飾をわかりやすくポリプロピレンで書いていますが、どの樹脂でも考え方は同じです)
赤文字が加飾のプロセスになります。
塗装
最も一般的な加飾方法が「塗装」です。
そして最もカラーバリエーションが豊富であるのも「塗装」になります。
樹脂を成形して出来上がったものに対して、表面を塗装膜で覆い、色をつけるやり方です。
塗装での加飾プロセスは以下の流れになります。

乳白色のポリプロピレンのペレットを作製し、乳白色の製品を成形します。
その後、塗装で狙いとする商品に加飾する流れになります。
材料着色(材着・原着)
自動車部品など大量生産で一般的な加飾方法が「材料着色(材着・原着)」です。
ポリプロピレン樹脂にフィラーや添加剤を混ぜ合わせる際に、着色料も一緒に混ぜて、ペレット自体に色をつけます。
そのため、成形品に色がついているため、塗装をする必要がなくなります。
ペレット自体を加飾することで、高コストの塗装工程をなくすことができるというわけです。
樹脂を成形して出来上がったものに対して、表面を塗装膜で覆い、色をつけるやり方です。
材料着色(材着・原着)での加飾プロセスは以下の流れになります。

材料着色とマスターバッチの違いは、着色料を混ぜるタイミングです。
材料着色は、材料混練時にポリプロピレンと混ぜ合わせます。
マスターバッチ(MB)加飾
マスターバッチ(MB)加飾も大量生産を必要とする自動車部品向けに用いられます。
着色料を高濃度に濃縮したペレットを、ポリプロピレン樹脂の中に数%添加することで、製品自体に色をつけるやり方です。
そのため、成形品に色がついているため、塗装をする必要がなくなります。
ペレット自体を加飾することで、高コストの塗装工程をなくすことができるというわけです。
マスターバッチ加飾プロセスは以下の流れになります。

材料着色とマスターバッチの違いは、着色料を混ぜるタイミングです。
マスターバッチは、成形時にポリプロピレンペレットと混ぜ合わせます。
最後に
今回は、【図解】樹脂の加飾方法まとめ について書いてみました。
今回まとめた加飾手法のメリットデメリットについては別記事でわかりやすくまとめております。
主に樹脂やゴム材料、材料リサイクルに関してわかりやすくまとめておりますので、皆さんのご参考になれば幸いです。
ゴムや樹脂材料でお困りなことがありましたら気軽にコメントいただければ、分かる範囲でご回答させていただきます。