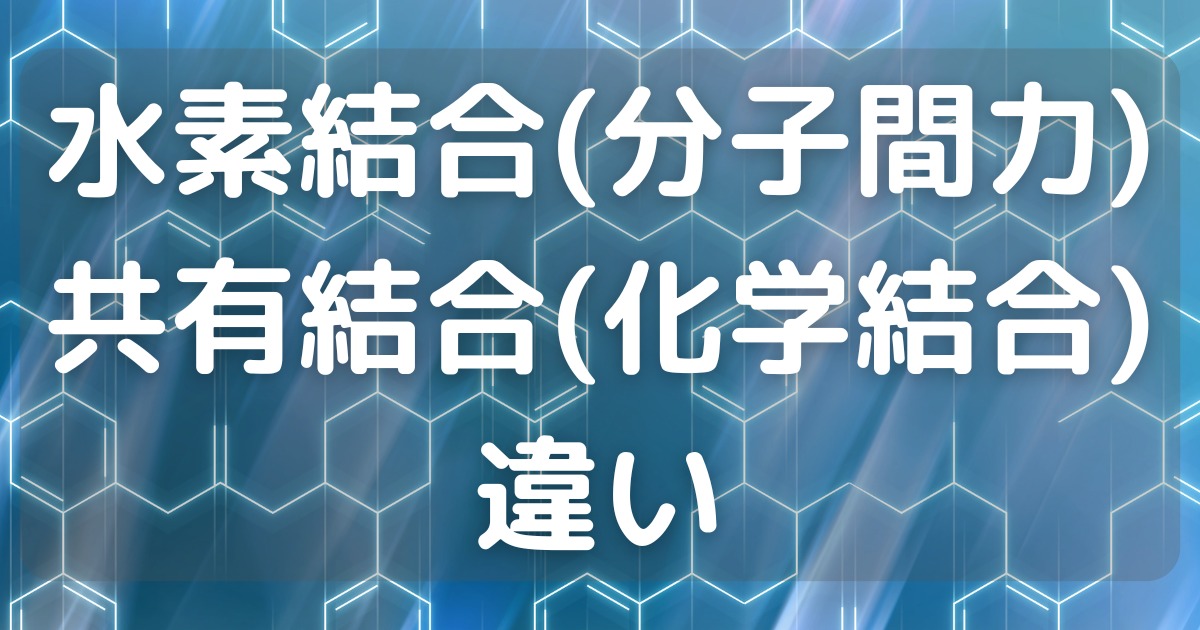今回は、ゴムの加硫メカニズム(トルクと時間の成形条件の関係)と加硫曲線 についてまとめました。
ゴム成形プロセス
ゴム材料の成形は以下2つのプロセスを経て行われます。
- ゴム練り工程
- 加硫工程
ゴム練り工程
ゴム材料に必要な添加剤を混ぜるプロセスです。
ゴムに補強材としてのカーボンブラックや、オゾン劣化防止のための老化防止剤、ゴム加硫を促進するための加硫促進剤などを混ぜ合わせる工程です。
ゴム練り工程は別記事に詳細をまとめております。
ゴム補強材のカーボンブラックについては、こちらでまとめております。
ゴム加硫工程
ゴム練り工程で添加剤を混ぜ合わせたゴムを加硫するプロセスになります。
この記事では、ゴムの加硫について詳細を書いていきます。
ゴム加硫とは
ゴムは、未加硫ゴムを架橋反応させ、加硫させることで部品として使用されます。
ゴムの加硫時間が短いとゴムの架橋が十分に行われず、狙いとする材料強度が発現しません。
一方で、加硫時間が長すぎると、ゴム分子鎖が熱劣化し、狙いとする材料強度が得られません。
そのため、ゴムの加硫工程は非常に重要な工程になります。
ゴムの加硫を利用した接着方法「加硫接着」については別記事で書いております。
加硫度試験
ゴムの加硫を測定する試験として、ゴム加硫度試験があります。
規格:JIS K6300-2 振動式加硫試験機による加硫特性の求め方
本試験は、未加硫ゴムの加硫特性を評価するもので、ダイ中空部に試料を充填し、一定のひずみを繰り返し与えることで発生する応力(トルク)を計測します。
ゴム加硫曲線
加硫曲線の見方については別記事で詳細に書いております。
ゴム加硫曲線 考察(考え方)
今回はさらに深く加硫曲線について見ていきたいと思います。
加硫曲線は以下のように考えることができます。

指標は大きく分けて2つあります。
加硫曲線_トルク
トルクの考え方として3つの見るべき指標があります。
- MH-ML
- ML
- MH

MH-ML
注目すべき指標は、MH-ML トルク差で、最大と最小のトルク差が大きいほど、材料の溶融時と硬化時の特性が大きく異なることを意味します。
ML
MLは、ゴムの分子量が低い、添加剤量が多い(相対的にゴム量が少ない)場合に低くなる傾向があります。
MH
MHは、架橋剤、架橋促進剤を増やすほど大きくなります。
加硫曲線_加硫時間
加硫時間の考え方で、見るべき指標は3つあります。
- Tc(10)
- Tc(50)
- Tc(90)

Tc(10)
トルク差MH-MLが10%に到達した時間がTc(10)で、加硫が10%進んだ時間を意味しています。
Tc(10)が、ゴムのスコーチしやすさ(焼けやすさ)の指標であり、Tc(10)が長いほどスコーチしにくいゴムです。
Tc(10)はスコーチタイムと似た指標になります。
Tc(50)
トルク差MH-MLが50%に到達した時間がTc(50)で、加硫が50%進んだ時間を意味しています。
Tc(10),Tc(90)と比較して確認する重要度は低いですが、Tc(10)からTc(90)にかけての傾きを確認する上で測定されます。
Tc(90)
トルク差MH-MLが90%に到達した時間がTc(90)で、加硫が90%進んだ時間を意味しています。
Tc(90)が加硫時間の指標になります。
Tc(90)が短いほど、成形が短時間でできることを意味しているため、大量生産の世界においては、Tc(90)が短いことが好まれます。
まとめ
ゴム開発において、最大と最小のトルク差(MH-ML)を小さくし、加硫90%到達時間 Tc(90) をいかに短くするかが求められます。
最後に
今回は、ゴムの加硫メカニズム(トルクと時間の成形条件の関係)と加硫曲線 についてまとめました。
別記事でゴム材料に関することを色々とまとめております。
お時間がありましたら読んでいただけるとご参考になると思います。
本記事が皆様のお役に立てていれば幸いです。
主に樹脂やゴム材料、材料リサイクルに関してわかりやすくまとめておりますので、皆さんのご参考になれば幸いです。
ゴムや樹脂材料でお困りなことがありましたら気軽にコメントいただければ、分かる範囲でご回答させていただきます。
■化学系最大級の本サイトでの広告等の御依頼がございましたらご連絡ください
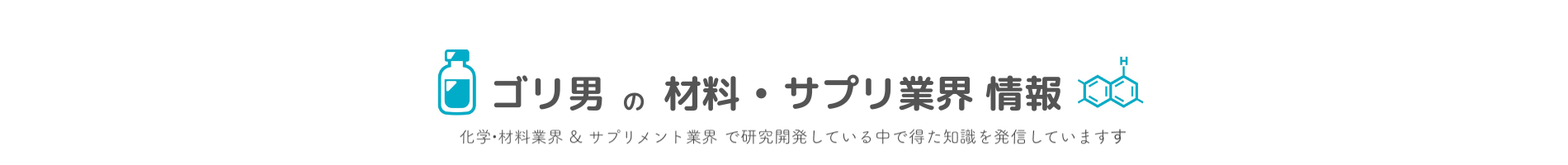



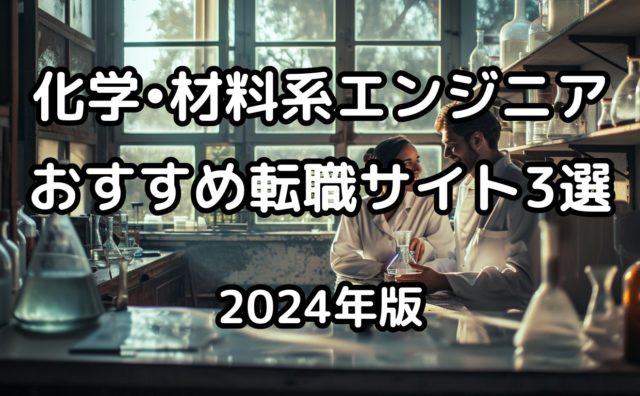


-640x396.jpg)