今回は、ゴムの摩耗種類とメカニズム(硬度と速度の関係) について書きたいと思います。
ゴム材料は、主に衝撃を吸収する防振用途や、接地する物質との摩擦力を利用するタイヤ用途に用いられます。
つまりゴム材料は、他物質と接して使われるため、他物質との擦れによるゴム材料の摩耗性は非常に重要な要素になります。
本記事では、ゴム材料の摩耗モードのまとめを行い、別記事で耐摩耗性向上について書きたいと思います。
摩耗とは
摩耗性は以下の式で表すことができます。
摩耗量 = 比摩耗量 × 荷重 × 摩耗距離
摩耗量は、比摩耗量と荷重と摩耗距離に比例することを意味しています。
比摩耗量
比摩耗量は材料固有の値です。
比摩耗量は、材料が硬いほど比摩耗量は小さくなります。
「硬い材料ほど削れにくく、柔らかいほど削られやすい」というイメージは想像しやすいのではないでしょうか。
荷重
荷重が大きいほど、摩耗量が大きくなります。
重いものを引きずるのと、軽いものを引きずるのでは、重いものを引きずった時の方が摩耗量が多くなるのはイメージできるのではないでしょうか。
摩耗距離
摩耗距離が大きいほど、摩耗量は大きくなります。
引きずる距離が長いほど、摩耗量は大きくなるというイメージです。
摩耗モード
摩耗には以下の4つのモードがあります。
- 凝集摩耗
- 疲労摩耗
- アブレシブ摩耗
- 化学摩耗
ゴムの摩耗に関して、どれか単一の摩耗モードが起こっているわけではありません。
どれかしらの摩耗がメインで生じ、その他の摩耗モードも多少なりとも関係しているイメージです。
凝集摩耗
凝着摩耗とは真実接触する粗さの突起の凝着部分が破壊されることによる摩耗で、滑り摩耗ともよばれます。
材料同士の凝着部がせん断されるときに、その一部が破断され、摩擦粒子として発生します。
消しゴムで文字を消す時に、消しゴムのカスによって消しゴムが大きく削れる現象です。
疲労摩耗
繰り返し応力により材料表面が硬化し、時間の経過によりひび割れが進行することによって発生する摩耗です。
長期間使用されたタイヤの表面がボロボロに剥がれ落ちる現象です。
アブレシブ摩耗
相手材の凸形状で引っかかれ、材料表面が掘り出される摩耗です。
爪で材料を引っ掻いた時に材料が削れる現象です。
化学摩耗
化学反応が起こり摩耗するモードです。
ゴムのオゾン劣化や酸化劣化により表面が摩耗して剥がれる現象です。
最後に
今回は、ゴムの摩耗種類とメカニズム(硬度と速度の関係) について書いてみました。
摩耗モードはいくつもあり、複数の摩耗モードが同時に生じることで、材料の摩耗を複雑にしております。
摩耗は摩擦力と密接に関係しておりますので、摩擦力について一度見ていただくと摩耗の理解が深まると思います。
そのほかにもゴム材料や、樹脂材料についてさまざまな記事にわかりやすくまとめております。
ゴムや樹脂材料でお困りなことがありましたら気軽にコメントいただければ、分かる範囲でご回答させていただきます。
■化学系最大級の本サイトでの広告等の御依頼がございましたらご連絡ください
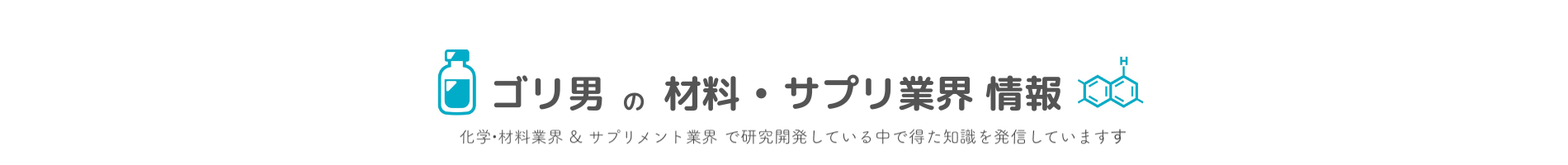
.jpg)
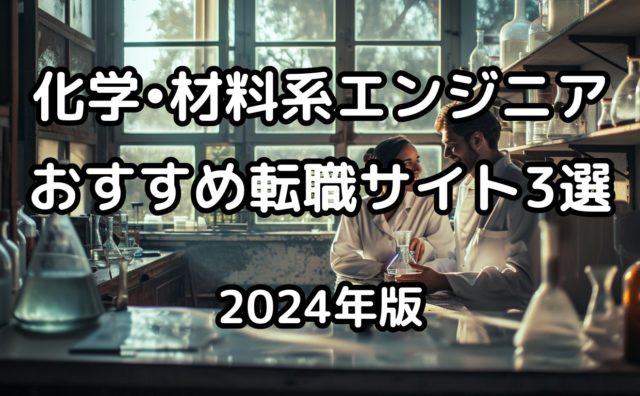


.jpg)
